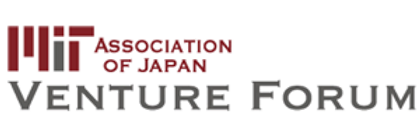MIT-VFJは24年間にわたり、毎年継続的にメンタリングプログラムを実施しています。
同プログラムでは、 MIT-VFJ登録メンターが徹底したメンタリング・アバイスを行い、事業計画の見直しやブラッシュアップを行います。
2024年開催のVMP(ベンチャーメンタリングプログラム)第24回ファイナリスト5人の方に順次お話を伺っており、今月は、株式会社Seed代表の井上 峻之介さんにご登場いただきます。
発達障害気味の子たちが情報系の仕事ができるように…AIを活用した独自の技術
- 大場
- 井上さんのビジネスモデルと会社について教えてください。
- 井上
- まず会社について説明します。
株式会社シードは、AI×教育の分野で3つの事業を行っています。
1つ目は、AIやシステムの受託開発を行っていて、顧客の課題分析から参画して、課題の解決に直結するAIとかシステムをオーダーメイドで開発しています。
2つ目が、包括的で最適な伴走サービスを行っていて、独自プロダクトの「Kaika」というものを活用することで対象者の特性を科学的にアセスメントして、学習や進路、生活のサポートを最適化する伴走サービスを提供しています。
3つ目はその独自プロダクトの「Kaika」を活用した教育支援を行っていて、専門学校や技能連携校などにAIとかシステム開発とかプログラミングの講師を派遣しています。
会社については、特許取得済みのAI技術を活用して、対象者の発言や行動記録といった言動情報や、体の動きや脳波といった身体情報分析することで、個々の特性に合わせた最適なカリキュラムを生成する独自プロダクト「Kaika」の開発や社会的普及を目指しています。
- 大場
- そのカリキュラムは、どんなジャンルで、どんな人が対象なのでしょうか。
- 井上
- 直近はプログラミングに限定しています。
プログラミングと言っても、データベースを設計するのが得意な人だったり、コーディングをするが得意な人だったり、デザインやUI・UXを設計するのが得意な人だったり、いろいろなタイプの人が対象です。
対象となる人の特性を分析し、データベース設計が得意なタイプであれば、あらゆる業界のデータベースを設計できるようになるというような目標に対して、最適なカリキュラムを推薦するというようなのもです。
初期はプログラミングに限定してカリキュラム推薦を行うんですが、将来的にはあらゆる業種・業界の包括的な…それこそ漫画家だったり、ミュージシャンだったり、いろいろな職種を含めた上で、その対象者にとって最適なカリキュラムを推進できるシステムを、将来的に作ることを目標にしています。
- 大場
- 例えば私がグラフィックデザイナーになりたいという場合、そのプログラムを受けると、1人で全てができるとか、よりパワフルに成長できるとか、カリキュラムに従っていけば、技術とかいろいろなノウハウなどが身に付いていくというような感じですか。
- 井上
- はい、おっしゃる通りです。
グラフィックデザイナーになりたいみたいな抽象的な目標を、コーチングとかコンサルみたいなところで、より具体的な目標に落とし込んでいって、その目標が達成できるようなカリキュラムを推進して伴走し、その目標達成に向かっていくような、そういうイメージです。
- 大野
- グラフィックデザイナーは一つのターゲットで、今後いろいろな分野に応用できる。でも、目下のターゲットはどんな人ですか。
- 井上
- 直近のターゲットは、発達に特性のある子や、少しグレーゾーン気味で、普段の学校教育に馴染めないような中高生、且つプログラミングとか情報系の分野に興味がある子です。
- 大野
- 情報系に興味のある子だけなんですか。
- 井上
- そうですね、直近は自分自身でサポートしようと思っているのですが、自分自身のできる対応範囲というのが、情報系のことに限られてしまうんです。
それで現在は、そういった子に対応しようと思っていますけど、今後広げていくにあたって、それ以外の子に対してもサービスを提供する予定です。
- 大野
- まとめると、情報系に興味を持っている中高生で、発達に特性のある子たちに、情報系の仕事ができるようになるためのカリキュラムを提供して伴走していくということでしょうか?
- 井上
- はい、おっしゃる通りです。
発達に特性のある子は天才タイプ、その才能を開花させる
- 大場
- 発達障害のある子たちにフォーカスしてスタートさせる理由はなんですか?
- 井上
- 発達障害というのは、個性が尖っていて…個性が尖り過ぎていている分、日常生活での必須の機能などが若干底がへこんでるみたいな…そういうイメージとして捉えています。
そういった子たちに、自分の作っているプロダクトがフィットするのではないかと考えてターゲットにしています。
- 大野
- 発達に特性があるってことは、あるものに特化しすぎていて、周りが目に入ってこない状態の人ということですね。
つまり天才タイプですね。
- 井上
- はい、そうですね、まさに。 自分は学生の頃から情報系の学部でAIの研究とかしていたのですが、発達障害の領域もすごく興味があって、その方面の教授などから話を聞いていく中で、やはり発達障害ってものすごい可能性があると思いました。
要はエジソンとやアインシュタインもADHDだったと言われていて、アインシュタインは幼い頃は言語障害でコミュニケーションがなかなか取れなかったのに、素晴らしい発明・発見をしていく。
そこの強みを伸ばすことに対して自分自身がわくわくして、その領域にとても興味があるという感覚を持っています。
- 大場
- なるほど。
自分が興味あることと得意なところを掛け合わせて、天才の方にはこういうところをサポートしていくと、より天才になるということに貢献できるみたいな、そんなモチベーションでスタートさせたという感じですか。
- 井上
- はい、そうですね。

三人三様のメンタリングの中で培われた言語化能力
- 大場
- VMP24に応募されたきっかけはなんですか?
- 井上
- 応募したきっかけは、伊藤さん(MIT-VFJ理事)に紹介してもらったことです。
自分が大学院の時にキャンパスベンチャーグランプリというビジネスコンテストがあり、そこでメンターをしてもらっていたのが伊藤さんでした。
大学院卒業後も定期的に伊藤さんにビジネスの壁打ちなどをしてもらっている中で、VMPを紹介されました。
その時はまだ起業する前だったんですが、自分自身のビジネスアイディアや思いはあって、メンターをしてもらえる方を探していたので応募しました。
- 大場
- VMPのメンターはどなたでしたか?
- 井上
- メインが西山さんで、サブメンターが富樫さん、理事の長谷川さんも入ってくれました。
- 大野
- 西山さんはすごく厳しかったでしょう。
- 井上
- 西山さんは厳しかったです。
でもよかったです。
自分の思いとかはあるんですが、そこを言語化することに、すごく苦労していたんです。
西山さんは、自分の思いや、なぜこの事業をやるのかみたいなところを、言語化することにとてもこだわっていました。
まずそこがすごく自分自身にとって成長できたという点です。
あともう1つは、西山さん冨樫さんと長谷川さんと自分で4人のメンバーで、ミーティングを週1回〜隔週で頻繁にやってもらい、そんな中で自分の言語化能力がどんどん高まっていき、自分のビジネスに対する思いがちゃんと話せるようになったという感覚があります。
厳しくしてもらってよかったなと思っています。
みなさんのサポートのおかげです。
- 大野
- メンターがそれぞれ得意な分野をお持ちで、個性もいろいろとあると思うのですが、井上さんから見てそれぞれのメンターはどうでしたか。
- 井上
- 西山さんは、何で自分がこの事業を行うのかをちゃんと言語化するとこにすごくこだわっていて、自分が出した「こういうことをやりたいです」ということに対しても、ツッコミをいただいて、どんどん深掘っていくような方でした。
その答えは多分自分しか持っていないので、自分がこれだという気持ちが多分答えだと思うんですけど、そこをすごく繰り返し考えさせてくれたようなメンターだと感じています。
西山さんとはそういう議論が多かったのですが、冨樫さんは自分と同じ目線に立って、ネクストアクションとしてどういったことをやればいいのかみたいな具体的なアドバイスをくれる方でした。
結構抽象的な話をしても、それを具体的に噛み砕いて、次こういうことをやればいいんじゃないかみたいなことを、サブとして提案してくれるような方だと思いました。
長谷川さんは事務局として入ってくれたので、メンターという関わりではなかったんですけど、抽象的な議論の中で、たまにぽろっとアドバイスとか発言してくれるんです。
その発言が自分にとってはあまり今まで見えてなかった視座のもので、その上解像度が高いという印象で、且つ自分自身の理解レベルにアジャストした上で言語化してくれていて、すごく理解しやすいんです。
長谷川さんの発言をメンタリング終わった後も反芻して、自分の視座や物事の解像度がかなり上がったという感覚を持っています。
- 大野
- 皆さんそれぞれお仕事をお持ちなので、それでいくと西山さんはエンジェル…投資家ですから、わかりやすい言語にするには?あなたの気持ちはどういうことなんだ?といった部分に特化して、しつこく聞かれたんだと思います。
じゃないと、投資家の人たちを説得できない。
富樫さんは割と大企業の幹部の人たちを、次にどういうふうにアクションを起こすんだみたいなお仕事の人だから、きっと井上さんに対してもそんなふうに接したのかもしれませんね。
長谷川さんはやはりベンチャーの人だから、その上皆さんの面倒を見ている立場の人だから、ボソッと的確なことを言ってくれる。
良かったですね、三人が三様で。
最も厳しいメンタリングに耐え抜いた人に与えられるHIROメモリアル賞
- 大場
- 何か具体的に、視座が上がるなとか感じたのはどんなことですか?
- 井上
- ちょっとこれも多分抽象的な…そもそも何かメンタリングは結構抽象的な話が多かったので、もしかしたら話として抽象的になっちゃうかもしれないんですけど。
自分の思いとしては、一人ひとりに合った学びを提供したい、一人ひとりに合った伴走をしたいということを思っています。
その中で、個別の一人ひとりの学びというのは、組織やチームの中では分断を生んでしまうんじゃないか。
一人ひとりに合ったことをやっても、それぞれが別々にそれぞれのやりたいことをやるということは、何か分断が生まれてしまうのではないか。
メンタリングの中でそういう話をしたことがあったんです。
自分は個人個人に良いサービスを届けたいみたいなそういう気持ちがあったんですけど、長谷川さんは広い社会の視点から見て発言されていました。
個人の特性に最適なサポートをすることと同時に、個人が利他的な心を持って他者を尊重できるようにすることが大切であることは、自分の中でもちゃんとメンタリングを通して理解できました。
長谷川さんの持っている社会的な全体をスコープとして捉える広い視点みたいなものは、見習わないといけないなと思いました。
- 大野
- どうしてこんなにメンタリングの話をするかというと、井上さんはVMP24でHIROメモリアル賞を取られたんですが、あの賞は、最も厳しいメンタリングに耐え抜いた人・チームに差し上げるんです。
MIT-VFJの理事長だった鈴木啓明さん(故人)という人がいて、とにかく厳しいし優しい。
厳しいことは優しいことの裏返しなんです。
今回、厳しいメンタリングを耐え抜いて、ファイナリストとなった井上さんという人にHIROメモリアル賞を差し上げることになったから、メンタリングについて、井上さんの思いや、反省やそういったものを聞きたいなと思って質問させていただいています。
何が最も自分のためになりましたか。
- 井上
- そうですね、自分の中でどこが厳しかったんだろうと考えたときに、なんでそれをやりたいのかみたいな議論が多くて、多分答えがない問いをずっと考え続けるみたいな半年ぐらいだったと思うんですけど。
これは今後も多分続いていくと思うんですが、やはり自分の気持ちをちゃんと言語化できたとき、それが自分のビジネスにとっての答えなんだということが、自分の中で腑に落とせたことは、メンタリングで一番の学びだったなと思ってます。
- 大野
- 逆に嫌だったなと思うことも、この際ですから言ってみてください。
例えば毎回メンタリングの時間が来るのが嫌でした?
それとも楽しみでした?
- 井上
- 自分はすごい楽しみでしたね。
嫌だったなっていうのは…どうなんだろう。
西山さんと結構ディスカッションすることが多くて。
自分はなぜこの事業をやりたいのかという思いを具現化できても、なかなかそれをただわからないというのでつっぱねられてしまったみたいなことがあって、自分の感情の底からの言葉を「わからない」で一蹴されたのが傷ついたところでしょうか。
- 大野
- 「どうしてそれはちゃんと言えないんだよ」などと怒られたとしても、それはメンタリングだからであって、例えば実際に投資家と話をするとしたら、怒るどころの話じゃなくて、単にほっとかれる。 「はいはいはい、お帰りください」みたいなことになっちゃうわけですからね。
その訓練がきっと少しは役に立ったんだろうなと思います。
- 井上
- はい、そうですね。
- 大野
- 西山さんは、投資家を説得するには「こういうふうにやらなきゃいけないんだけど、全然駄目だよ」と思ったのかな。
でもそれが訓練によってできるようになったわけですよね。
- 井上
- そうですね。自分の気持ちとかをちゃんと言語化するみたいなところは、すごくこだわっていますね。
- 大野
- だって最初の面談審査で発表を聞いたときは「この人、何言ってるのかよくわからない、何がやりたいのか全くわからない」という感じだったんですよ。
- 井上
- はい、ええ。そうですよね。
- 大野
- でも最終発表会のときには、きちっとプレゼンができているし。
すごい進歩でした。
- 井上
- はい。おかげさまで、ありがとうございます。
自分が一生続けているビジネスだと確信を持つまでに至ったメンタリング
- 大場
- メンタリングと発表を受けて、今何かビジネスが具体的にすごく変わったとか、こういう課題を抱えてるけどメンタリングを受けたことによって克服できそうとか、今の時点での井上さんはどんな感じなんですか。
- 井上
- メンタリングを受けて変わったことは、2つあります。
1つ目は、本当にこれから一生続けていけるビジネスだなと自分の中で落とし込めたので、実際にメンタリングの中で起業しようと思い、去年の12月に会社を作りました。
もう1つが、持続可能でしかもスケールするようなビジネスに、ちゃんとアイディアを昇華できたなという気持ちがあります。
元々自分はエンジニアで、知り合いの人からプログラミングのお仕事をもらってお金をいただくみたいなのは個人事業主としてやっていて、その中で教育にすごく思いがあって、そこの分野で何か起業したいという気持ちがありました。
アイディアを練ったり、メンタリングプログラムに参加している中で、何か自分が一生続けているようなものに、アイディアが変化しました。
- 大場
- 今仲間が増えてきているとか、会社としてこんな状況になったみたいな変化もあったんですか。
- 井上
- 実際に伴走サービスをまず1人で1年間ぐらいちゃんときちっと作ってから、来年から仲間を増やしていこうと思っています。
例えば自分がやっているようなAIで発達に特性のある子の分析をするということを、筑波大の先生に話したときに、興味を持ってくれてアドバイザーとして関わってもらい、進んでいたりします。
それもメンタリング中に言語化スキルとかがついたおかげで、多分自分のやりたいこととかを話せるようになったからです。
でもこれからどんどん仲間が増えていくんだろうなみたいな感覚は持ってますね。
そのために自分がやりたいことの土台を作りきって、仲間に入ってもらえる状況を早く作りたいなと思ってるような状況です。
マネタイズの課題解決の糸口もメンタリングの中にあった
- 大野
- 具体的に何人ぐらいの伴走をしているのですか。
- 井上
- 今はまだシステム開発が終わった段階で、運用自体はできていないんですが、今年中に3人ぐらいの人を見つけて、1人で実行したいと思ってます。
- 大野
- 1人で3人面倒見る。 なるほど。でもそれだと全くマネタイズできないですね。
- 井上
- そうですね。はい。
- 大野
- どうやってお金を稼げるようにしていくんですか。
- 井上
- まず初年度は、受託システム開発の方も頑張って、そこでうまく食べていけるぐらいのお金を稼ごうとは思っています。
伴走する人を広げていくにあたっては、大学生とかに声をかけて、実際に伴走者を雇って、その方に伴走してもらって自分が伴走者のマネジメントをするみたいな。
その後はマネジメントも、経験があるビジネスマンの方とかにお願いして、自分がいなくても回るような仕組みを3年ぐらいで作れたらなと思ってます。
- 大野
- つまり、伴走者を育てなきゃいけないってことですね。井上さん自身が。
- 大場
- 伴走者が増えていき、プログラムを実際に使ってくれる人の方はどうやって増やそうとされているんですか。
- 井上
- 最初は不登校の親の会などに参加して、ニーズがある人に声をかけていこうと思っているんですけど、将来的にはサービスが良ければ口コミでどんどん広がっていくかなというイメージを持ってます。
- 大野
- 不登校の子とか発達に特性がある子たちは、社会の大きな力になれるんだよというのを見せてあげたいですね。 そうしたら素晴らしいビジネスですよね。
- 井上
- 本当に全く可能だと思ってるので。
自分は学生の頃に不登校の子の家庭教師をやっていたのですが、自分は不登校の経験がなかったので、不登校ってどんな子かをわかっていなかったんです。
実際に不登校の子の家庭教師とかやっていくと、その子たちは本当にポテンシャルはあるし。
要はその子とかも自律神経機能が若干弱くて朝起きられないとか、そういう子だったので、本当にその子に合った支援ができれば全然問題なく社会で活躍できるなと感じました。
すごく可能性はあるなと思っています。
- 大野
- AIを使ったカリキュラムを作るということですよね。
AIはどんな答えを出してくれるんだろうかという疑問が私にはあって。
結局AIに欲しい情報を出してもらうためには、必要な情報をインプットしなきゃいけないですよね。
ということは、AIはもちろん頑張ってくれるんだけれども、その前に、井上さんご自身と会社のスタッフ全員が、AIに対して的確なプロンプトを入れてあげないといけないですよね。
つまり、結局は井上さんがしっかりしてなきゃいけない。
- 井上
- まさにそうです。
全く理論がないものを突っ込んでも、なんかよくわかんないものが出てくるだけなんです。
何でそのサービスをするのかとか、何でそういう支援をするのかというのを、ちゃんと言語化するみたいなところに、こだわり続けていたら、いずれはより自動化されて、より少ない人件費とかでできるようになるみたいな、そういうイメージを持ってます。
- 大野
- ということは、井上さん自身が的確に言語化する訓練が、メンタリングで身についたとすると、素晴らしいメンタリングの機会を得たということになりますね。
- 井上
- 本当にまさにそうですね!
他にはないVMPの特徴 メンタリング合宿
- 大場
- 何か学生の頃もコンテストを受けたとおっしゃったと思うんですが、VMPとの大きな違いって何かありますか?
- 井上
- 長い期間メンタリングをしてくれて、ブラッシュアップするところに多分重点を置いてくれているみたいなところが大きな違いだと思います。
あとはもう1つ、合宿です。
自分は学生時代にビジネスコンテストに出たんですけど、泊まり込みの合宿があるコンテストはなかったです。
自分はVMPの合宿がめちゃくちゃ良かったなと思っています。
本当にいろいろなメンターの方に、いろいろな視点で多角的にアドバイスをもらえる経験って本当に探してもないので、それがすごく良かったですね。
- 大野
- 学生時代のはキャンパスベンチャーグランプリですよね。
- 井上
- キャンパスベンチャーグランプリと、全国大学ビジネスコンテストと、立命館大のベンチャーコンテスト、その3つです。
- 大野
- みんなそれぞれコンテストだから、競うだけのものなんでしょうか?
- 井上
- 立命館大は複数のメンターの方にアドバイスをいただくみたいなことはあったんですけど、泊まり込みとかはなかったですね。
- 大野
- キャンパスベンチャーグランプリは日刊工業新聞がずっと昔からやっていて、MIT-VFJも協賛して審査員を出したり、メンターを派遣したり、提携してやっています。
- 井上
- そうですよね。
MIT賞っていうのもありますよね。
- 大野
- MIT賞あります。 それでメンタリングが受けられるんですよ。
- 井上
- そうなんですね、なるほど。
すごい繋がりを感じています。
キャンパスベンチャーグランプリに出ていなかったら、伊藤さんとの繋がりがなかったら、VMPに参加しなかったかもしれないので、そういった意味でも、やはり出てよかったなって思いますね。
- 大場
- 未体験なので質問します。合宿ってどういうことをやって、合宿を経てどんなふうに井上さんはジャンプアップしたんですか。
- 井上
- 合宿は 1泊2日で、まず最初にどういったビジネスを考えてるのかを、ファイナリスト候補の5名でプレゼンします。
それに対して、普段受け持ってもらっていないメンターも合わせて、メンティーがいろいろなメンターに対してぐるぐる回って、いろいろな角度でアドバイスをいただいて。
それを一晩でブラッシュアップできる人はブラッシュアップして、中間発表といって10分ぐらいのプレゼンをし、それに対して質疑応答があります。
そのときに、本当にいろいろな角度で、いろいろなアドバイスをいただけて。
川北さん、入野さんなど、普段担当してもらっていないメンターの方からも、アドバイスいただきました。
自分はその合宿中に、このビジネスは多分持続可能だし、何か今後も続けていけるなという感覚を持った気がします。
川北さんのアドバイスが結構大きかった気がしますね。
自分は、中高生の不登校支援とかやったり、家庭教師をやっている関係で、中高生をターゲットにしてみたんですけど、何かもっと企業側のニーズとかもあるんじゃないかとか。
いろいろな観点のアドバイスを川北さんがしてくれて。
将来、その子が成長して就職するタイミングで、企業側のニーズがあるんじゃないかみたいな話をしていただいて、その観点の感覚は持ってなかったので、いろいろな広がりを感じました。
合宿のアドバイスを経て、何かイメージできたという感覚があります。
メンターや関係者との繋がりを持ち続ける
- 大野
- 生かしていけそうですか。
- 井上
- はい、目指していきます。いけると思います。
- 大野
- 川北さんはすごく経験豊富で、ご自身が起業家で。
潤という名前なので、私はいつもサイボーグジュンと言っています。
すごい人なんですよ。
怪物です(笑)
- 井上
- 入野さんからも技術的なアドバイスをいただけました。
技術的にコストが少なく、且つニーズがあるところがどこなのか、というようなことは入野さんにメンタリングしてもらって。
それも自分の中のエッセンスとして、ビジネスアイディアに入り込んでる気がします。
- 大野
- いいですね。入野さんもすごい人ですからね。
- 大場
- メンターとは今も繋がっているんですか?
- 井上
- Facebookでは繋がってはいるんですけど、相談とかはしてないですね。
メンタリング中に本当にいろいろなアドバイスをもらったので、まずはそれを実践して、今後この人にこれを相談したいみたいになればいいなという気持ちで今はやってます。
- 大野
- 関わった人たちは、みんな本当に普段ではなかなか会えない、得がたいすごい人達なので、甘えて何でも頻繁に相談し、コンタクトを密に取っていったらいいと思います。
- 井上
- 本当にそうだと思いました。
その人達をわくわくさせる動きはしたいですね。
入野さん、川北さん、長谷川さんにはない部分が、自分にはあると思うので、まずはそこを発揮できるように頑張りたいなという気持ちはものすごくありますね。
- 大野
- いいですね。
井上さんには、入野さんにも、川北さんにも、長谷川さんにも、西山さんにも、富樫さんにもない、良い部分がぜったいにあるから。
それが井上さん自身のValueだと思いますよ。
それを言語化していくというのが大事でしょうね。
- 井上
- そうですね。
まだ言語化できてないですね。
本当に自分だけにしか当てはまらないみたいなことについては、確かにずっと考えてます。
- 大野
- ありますよ。
それは自分で考えても、意外と見つからなかったりするので、みんなに聞いてディスカッションする機会を作るといいと思います。
- 井上
- 確かにそうですね。ありがとうございます。
VMPの応募を考える方へのメッセージ
- 大場
- VMPの応募を考えている方にメッセージをいただけますか。
- 井上
- ぜひ応募してほしいと思っています。
応募を考えているということは、少なからず起業に関心を持っていると思うので。
VMPの関係者の皆さんに、自分の想いや、自分が持っているビジネスアイディアに対する熱とかが伝われば、本当にそこに想いを返してくれる。
関係者の方が全員そうだと思うので、応募してみたらいいですし、応募してなくなるものはないので、応募を考えているのだったらぜひ応募してほしいなと思います。
- 大場
- みなさんの背中を押してくださる言葉をありがとうございます。
本日はお忙しいところ、ありがとうございました。
井上 峻之介(いのうえ・しゅんのすけ) 氏 プロフィール
1998年、千葉県市川市生まれ。2023年、筑波大学大学院 情報理工学位プログラム修了。
在学中よりシステムの受託開発に携わる一方で、不登校支援団体の世話人として活動。
不登校の生徒と支援者の間にあるジェネレーションギャップの課題を実感する。
この経験をもとに、一人ひとりに寄り添った学習支援の実現を目指し、2024年に株式会社Seedを設立。

聞き手 大場さおり
NTTドコモに新卒入社後、コーポレートブランディング、コーボレートコミュニケーションの分野に長らく従事。
展示会等のイベント、広告制作、ドコモ未来フィールドの立ち上げ等対外発信戦略の立案と実行を担う。
2025年より兼業でMIT-VFJ広報を担当。
「未来を担う人々が日本、さらにグローバルへ羽ばたいていけるように」「日本のビジネスや伝統文化などの良さを海外・国内と広く広める」を自らのmissionととらえ、ファイナリストやMIT-VFJの情報発信を担う。